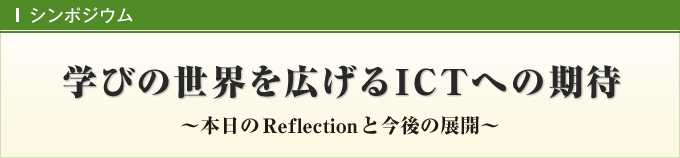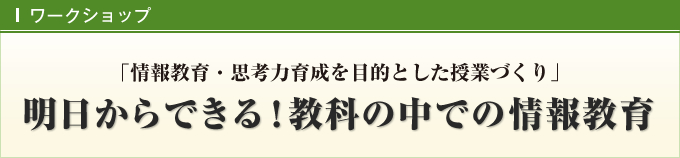- HOME >
- 研究会・セミナー >
- 全日本教育工学研究協議会 全国大会 開催予定と結果報告 >
- JAET2015 富山大会 >
- 公開授業、シンポジウム、ワークショップ
本大会では、富山市内6校で36の授業が公開された。公開授業校の一つ、富山大学人間発達科学部附属小学校の4年理科「水の3つのすがた」の授業では、沸騰した時に出る泡の正体を調べるため、児童が実験の様子をタブレット端末で撮影し、その写真や動画を用いて意見を交わした。また、富山市立芝園中学校では、全教室に常設された実物投影機とプロジェクタを使用し、教材や生徒のノートを提示するなど、普段のICT活用の授業が公開された。

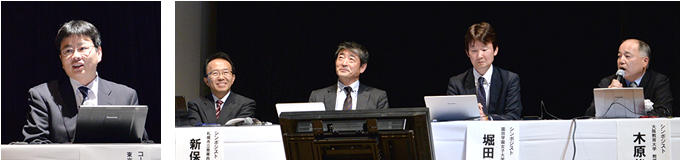
シンポジウムでは、高橋純・東京学芸大学准教授がコーディネータを務められ、「学びの世界を広げるICTへの期待」をテーマに議論が交わされた。
冒頭、高橋先生はICTの活用状況に触れ、富山市はICT機器の導入・常設がスクール・ニューディール政策の前に行われ、ICT機器の研修に熱心に取り組んだことを紹介。2015年度は富山市内全65校において、1、2学期で20万時間もICTが使われ、日常使いが現実となっていると報告された。
新保元康・札幌市立発寒西小学校校長は、「情報化は教育の質の向上につながる。しかし、ICT機器を入れただけでは、質の向上につながらない。ICT機器を常設し、設置する位置まで固定してインフラ整備を行う。また、授業の研修も行って日常的なICT活用を進め、学校の経営全般を見直し、徹底すること。これらを合わせて行うことが重要である」と述べられた。
堀田博史・園田学園女子大学教授は「ICTは、自分の考えを可視化したり言語化したりすることに、たっぷりと時間を取ることができる。また、活用を通して次第に古典的な使い方(かつてコンピュータ教室で、情報をまとめたり調べたりするような使われ方)に集約され、そうした方法での学習活動が日常化されていくと思われる。新たなチャレンジも必要だが、学びの世界を広げるICT活用は、そうした古典的なICTに軸足を置くことが大切であるということに気づくことが必要」と話された。
金俊次・米沢市立東部小学校校長は、「ICT機器の活用は授業の質の向上につながる。しかし、そのためにはICT機器を日常的に活用し、例えば実物投影機なら『何を見せて、何を見せないか』といったことを考え、授業の本質に迫る課題と向き合う必要がある。まずはICTを使った学習の規律と習慣をつくり、段階を踏んだ情報化が求められる」と強調された。
木原俊行・大阪教育大学教授は、「毎日毎時間、ICT機器で教材をわかりやすく提示することで、子どもたちは授業がわかるようになり、自分の可能性を信じられるようになる。こうしたICT活用の広がりには、先生方の学び合いが重要。全体として組織化していこうとする管理職やリーダーの意思決定や判断、マネジメントが重要である。教育の情報化は各々の学校が基盤であり、1年単位ではなく、3年、5年など中期計画で活用を考えてほしい」と結ばれた。
 ワークショップのセッションではICTを活用した授業づくりや情報モラル指導、情報教育などをテーマに9つのワークショップが行われた。
ワークショップのセッションではICTを活用した授業づくりや情報モラル指導、情報教育などをテーマに9つのワークショップが行われた。
「情報教育・思考力育成を目的とした授業づくり」のワークショップでは、木村明憲・京都教育大学附属桃山小学校教諭、佐藤和紀・東京都北区立豊川小学校教諭、若松俊介・京都教育大学附属桃山小学校教諭らが登壇され、木村教諭が中心となって開発された「学習支援カード」「情報ハンドブック」を紹介。日常の授業での活用に向けて、参加者と議論を交わされた。
 学習支援カード(パワーチェックカード)は、「情報活用の実践力」を児童でもわかる文言で表し、学年ごとに情報を「集める」「まとめる」「伝える」の3つの観点で問題解決の流れに合わせて整理されている【図1】。さらに、学習支援カードの各項目を絵や写真でわかりやすく説明した情報ハンドブックと併せて活用させることで、家庭学習の充実にもつながるという。
学習支援カード(パワーチェックカード)は、「情報活用の実践力」を児童でもわかる文言で表し、学年ごとに情報を「集める」「まとめる」「伝える」の3つの観点で問題解決の流れに合わせて整理されている【図1】。さらに、学習支援カードの各項目を絵や写真でわかりやすく説明した情報ハンドブックと併せて活用させることで、家庭学習の充実にもつながるという。
若松教諭は、自身の学級での学習支援カードの活用効果を発表され、児童が自分の情報活用の実践力を把握できるようになったことや、色などを使い分けて自主学習ノートを書く児童が増え、情報を整理して表現するようになったと報告された。
続いて発表された佐藤教諭は、学校での学習支援カードの活用推進事例を報告。校内での普及に向け、先生方の関心が高かった「情報モラル」の項目も加えた学校独自の学習支援カードの作成に着手されたこと。また、作成過程で、多くの先生方が普段の授業で取り組んでいる内容が多いことやICTを使わなくても情報活用の実践力が育成できることに気づき、情報教育に対する理解が深まったと報告された。
今後について木村教諭は「学習支援カードをもとに、児童と一緒にルーブリックを作って学習に臨むことでより学習効果が高まることがわかってきた。さらに研究を進めるとともに、先生方が拡大して提示できるようにデジタル版も提供したい」とさらなる改良に意欲を示された。
研究会レポート 全国教育工学研究協議会全国大会 JAET2015 富山大会
【基調講演】広げよう学びの世界 − Innovation & Challenge in Toyama −
山西 潤一(富山大学教授 / 日本教育工学協会常任理事)
公開授業、シンポジウム、ワークショップ
【講演】学びの世界を広げるICTへの期待
堀田 龍也(東北大学大学院情報科学研究科教授)
(2015年12月掲載)