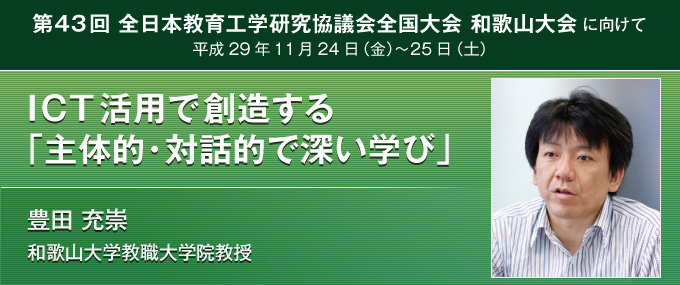- HOME >
- 研究会・セミナー >
- 全日本教育工学研究協議会 全国大会 開催予定と結果報告 >
- 第43回 全日本教育工学研究協議会全国大会(和歌山大会)に向けて
教育の転換点に立つ意義深い大会に
アクティブ・ラーニングを行うこと自体が目的ではなく、
その視点に立って授業を改善し、
主体的・対話的で深い学びをめざす
平成29年3月に新しい学習指導要領が公示され、「戦後最大の改革」と見出しがつくほどセンセーショナルに報道されたりもしました。教育の内容・方法が変わるため、教育現場では日増しに期待感と不安感が広がっている様子もうかがえます。この激動の教育改革が叫ばれる中、和歌山の地にて「全日本教育工学研究協議会全国大会」が開催されることは大変意義深いことであり、新学習指導要領の施行に向けた指針を示せるような大会にしたいと考えています。
さて、2年前に和歌山大会の開催が決まったときは、「アクティブ・ラーニングへの転換」という話題が先行していましたので、当初はアクティブ・ラーニングの推進のためにICTを有効活用するといった趣旨の大会テーマに設定したいと考えていました。しかし、最終的には中教審答申にて「主体的・対話的で深い学び」というフレーズが先行し、その学びを実現するために「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善」が必要であるというニュアンスにまとめられたといえます。
アクティブ・ラーニングを行うこと自体が目的ではなく、その視点に立って授業を改善し、主体的・対話的で深い学びをめざすというアプローチは多くの教育現場で共感を得ているといえますが、多忙化・学力保障・トラブル対応等々に追われる教育現場では、その実現を危惧していることも確かです。
そこで、本大会のテーマを、『ICT活用で創造する「主体的・対話的で深い学び」』とシンプルに掲げ、ICTを活用して新しい学びにつながる授業をどのようにつくりだしていくのか、深い学びを実現する手段としてICTをどう有効活用していくのかを参加者の皆様と考えていきたいと思います。
【学校情報化認定校】から学ぶ機会
情報化先進校を表彰するとともに、
先進校の取り組みを広く周知していただくためのシンポジウムを予定
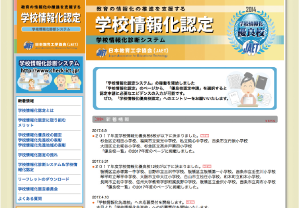 学校情報化認定サイト
学校情報化認定サイト
(http://www.jaet.jp/katudou/nintei/)
日本教育工学協会(JAET)は、教育の情報化の推進を支援するために、総合的に情報化を進めた学校を「認定」し、その努力を称えるとともに、今後情報化をめざす学校へのモデルとなっていただくという趣旨の事業をおこなっています。2014年から開始して徐々に認知度が向上し、今年で300校を超える「学校情報化優良校」を認定することができました。
優良校のそれぞれから提出される「情報化の特色」や授業場面を参照していると、各校の取り組みのカラーが出ており、それぞれのスタンスで教育の情報化を推進してきたことが分かります。「学力向上」のためにデジタル教科書や電子黒板にて学習効率を向上させた学校、思考力・表現力の発揮のためのICTという位置づけの学校、図書室の活用を軸に情報活用能力の育成を念頭に置いた学校など、約300校分のデータが蓄積されたこのサイトは学校情報化の推進・普及のノウハウが詰まった国内最大のデータバンクといえます。未登録の学校がありましたら、ぜひアクセス・登録をお願いできればと思います。
これらの情報化優良校の中から更に「情報化先進校」を選抜して表彰していますが、今年の全国大会では、この情報化先進校を表彰するとともに、先進校の取り組みを広く周知していただくためのシンポジウムを予定しています。「先進校の表彰」は例年5校程度の「狭き門」となっていますが、そこに選ばれる学校には、やはり多々理由があります。情報環境整備、人的支援体制、カリキュラム、研修の工夫や研究基盤づくり、管理職のリーダーシップ、地域の要請等、さまざまな要因が絡み合い相乗効果をもたらしているといえます。今大会では、この「先進校」の担当者を招聘し、どういったバックグラウンドを持っているのかを明らかにしたいと思います。
ただ、和歌山に本大会を誘致しておきながら非常に申し上げにくいのですが、本県にはまだ情報化優良校としての認定を受けた学校がなく、数少ない「認定空白県」ともいえます。今大会をきっかけとして機運を高めたいと思いますが、まずは冷静に改めて先進校の持つ情報化の要因に学び、本県には「何が足りないのか」という点も明らかにできたらと考えています。
バリエーション豊富な公開授業の設定
従来の授業に融合した形の実践から、
学習者用デジタル教科書の活用や次期学習指導要領を先取りしたプログラミングまで
 和歌山大学教育学部附属小学校 3年 理科 「磁石のふしぎをさぐろう」の授業
和歌山大学教育学部附属小学校 3年 理科 「磁石のふしぎをさぐろう」の授業
今回の公開授業校は5校とこれまでの大会からすると小規模であり、そしてその大部分がICT活用研究における公開授業が初めてといえます。昨年度のICT教育先進県である佐賀県、一昨年度の古くからのICT授業研究基盤のある富山県らと比較されてしまうかもしれませんが、設備や研究基盤が乏しい中で手を挙げていただいた授業者の皆様のモチベーションは非常に高く、公開授業のバリエーションも豊富です。
まず、和歌山大学教育学部附属小学校は、ICT活用授業研究会をのべ10回にわたり実施してきた常連校です。ただし、ICT設備環境はそれほど充実しているわけではなく、その整備は学校の自助努力に負うところが大きいといえます。「これまでの研究を踏まえた上で、新しい取り組みを見てもらいたい」との意向から、「学習者用デジタル教科書」やプログラミング教育・情報モラル教育等、趣の異なる授業が公開展開される予定です。また、附属中学校は100台を超えるモバイル端末が導入されており、これまでの協働的な学びのツールとしての蓄積もあるため、グループワークでの有効活用を中心に授業が組み立てられる予定です。ICT活用授業として特に意識をせずとも、普段使いも浸透している学校といえます。
また、特別支援教育におけるICT活用も注目されているため、附属特別支援学校では、学習を支援するツールとしてのICT活用や生徒たちの交流ツールとして生徒自身がタブレットを活用するといった場面も見込まれています。
和歌山県内屈指の進学校である桐蔭中・高等学校は中学校と高校からそれぞれ授業が公開されます。中学校部は全教室に早くから電子黒板機能付きプロジェクタが常設されており、ICTの日常化は達成されているといえます。
一方、桐蔭高校では教員用のタブレットPCを用いた授業が展開される予定です。今年の9月から県立高校においては、県内一斉に校務用PCがすべてタブレットPCに置き換えられ、校務用PCと教材提示用PCを兼ねて活用するという方針になります。二学期からの導入となりますので、授業者にとっては「つかい始め」の頃になりますが、逆にいうと、従来の授業に融合した移行期の様子がうかがえるかもしれません。
そして、最後に和歌山市立伏虎義務教育学校ですが、「義務教育学校」という言葉は初めてお聞きなる方もおられるかと思います。2016年では全国で22校しか開設されておらず、もちろんJAETの全国大会で義務教育学校が公開されるのは初めてです。この4月からの新規開設校ということもあり、学校全体の取り組みというよりは、ICTをこれまで有効活用してきた2名の方の授業となります。義務教育学校というコンセプトにおいて、児童生徒の9年間の成長の中で、連続性のある指導をどのように行っているのかといった場面がみられるかと思います。
以上のように公開授業校全体を通して、指導者用デジタル教科書を用いたスタンダードなICT活用実践から、本年度発売の学習者用デジタル教科書の活用や次期学習指導要領を先取りしたプログラミングまでを網羅しています。また、附属小学校では「複式学級」の授業が公開されたり、支援学校では普通校との実際の交流場面を公開日に設定していただいていたりと、そのバリエーションの豊富さではこれまでの大会にも負けてはいないはずです。
なお、この5校はメイン会場を中心に半径3km以内に位置しています。小・中・高・支援学校がそれぞれのICT活用の有効活用場面を共有することで、今後の和歌山の「教育の情報化」を牽引する役割を担って欲しいと考えています。
皆様、ぜひ11月24~25日は和歌山にお越しいただき、上記のような各校の状況を把握した上で、忌憚のないご意見・ご指導をお願い致します。
第43回 全日本教育工学研究協議会全国大会 和歌山大会
大会テーマ:ICT活用で創造する「主体的・対話的で深い学び」
- 期日
- 平成29年11月24日(金)~11月25日(土)
- 会場
- 和歌山県民文化会館
- 公開授業校
- 和歌山大学教育学部附属小学校 / 和歌山大学教育学部附属中学校 / 和歌山市立伏虎義務教育学校(小・中学校) / 和歌山県立桐蔭中学・高等学校 / 和歌山大学教育学部附属特別支援学校
1日目 11月24日(金)
| 内容 | 会場 | |
| 9:30~ | ● 公開授業 | 各学校 |
|---|---|---|
| 13:00~ | ● 開会行事 | 和歌山県民文化会館 |
| 13:20~ | ● 基調講演
「次期学習指導要領とICT活用の必然性・可能性(仮題)」 文部科学省生涯学習政策局情報教育課 |
|
| 15:00~ | ● シンポジウム
「“学校情報化優良・先進校”から情報化の達成・成功要因を探る(仮題)」 |
|
2日目 11月25日(土)
| 内容 | 会場 | |
| 9:00~ | ● 研究発表 | 和歌山県民文化会館 |
|---|---|---|
| 13:30~ |
● ワークショップ
|
|
| 15:45~ |
● 本音で語る総括トーク
ICT活用で「主体的・対話的で深い学び」は実現できるか |
|
| 16:45~ | ● 閉会行事 | |
※予告なくプログラム内容が変更となる場合がございます。
(2017年8月掲載)