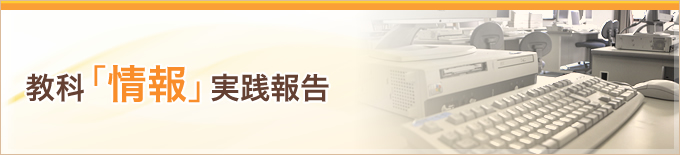- HOME >
- 情報教育 >
- 教科「情報」実践報告 >
- 情報技法習熟を目的とした旅行計画の考察
情報技法習熟を目的とした旅行計画の考察
磯崎 喜則(日本学園中学校・高等学校 教諭)

【あらまし】
高校情報実習で従来行われている「旅行計画」をさまざまな情報技法を駆使して行う実習を考えた。実習者(作成者)の立場を「旅行業者」とし(仮想的な)「顧客」に対して「チラシ作成」したり、(同級生=現実的な) 顧客に対して「プレゼンテーション」を行ったりすることを目的とした。
「顧客」の好みを探り、旅行チラシにとって必要な情報を入れたチラシを「ペルソナ・シナリオ法」「マインドマップ」などの情報技法を使う授業を考察する。
【1】研究の背景
一般の人たちにとって高校情報はコンピュータ教育と認識されている場合がある。情報教育の初期においてのコンピュータリテラシ教育はある一定の意義があったけれども、現在のようにコンピュータ利用が多岐にわたってくると一般教養としてのコンピュータリテラシでさえ広範囲となる。高校情報における一般教養的なコンピュータリテラシをどのように定めるかも難しくなっている。
KJ法やブレーンストーミングなどの情報技法を学習させることがある。しかし、KJ法・ブレーンストーミングともに正式な方法で行うのは一般の高校生にとってはハードルが高い。
高校生にとってわかりやすく実用的な情報技法を用いて効果的な情報実習を考察してみる。
【2】旅行計画の考え方
個人的な旅行計画であれば、厳密に計画することなく、その場の雰囲気や状況に合わせて旅行計画を適宜変更することはある意味旅行の醍醐味であり何ら問題はない。しかし、このような計画では情報の実習として行いにくい。
そこで、旅行業者になったつもりで顧客が満足する計画を立てるという実習を設定した。これにより実習のスタートとゴールが明確になった。
【3】ペルソナ・シナリオ法
旅行は個人的な趣味により大きく変化をする。旅行業者の用意している旅行プランが沢山あるのは多くの顧客が満足するように各種条件を変えて用意しているためである。デザイン関係で活用されている「ペルソナ・シナリオ法」の一部を利用して顧客分析を行う実習を考えてみた。
ペルソナ・シナリオ法とは、顧客の満足度を高める為には、万人向けの計画を立てるのではなく、顧客集団を代表する特定の人物(ペルソナ)を仮想し、そのペルソナの個人情報を明確にした人物像を特定したうえで、ペルソナが満足する計画を立てるという方法である。
企業が実際行うペルソナ・シナリオ法は詳細なアンケート調査を行うなど大掛かりな手法であるから高校生の実習では同じクオリティで行うことはできない。そこで、ペルソナの条件を日本に住む高校1年生男子と限定し、生徒たちが想像しやすいペルソナ像で行った。
アンケート調査の代わりに、生徒たちが生まれてから今までの間で付き合ったり、知り合いになったりした同年代の男子全体を母集団と考えた、簡易的なペルソナ・シナリオ法で行った。
これにより自分好みの旅行を楽しく計画するだけの実習ではなく、顧客(ペルソナ)が満足する旅行を行うためにどのような情報を処理しなければいけないかを意識させることができた。
【4】実際のチラシ情報を分析
プロの旅行業者が作成した本物のチラシを用意して(旅行業者から余ったチラシを大量にもらった)旅行チラシに必要な項目を挙げさせた。
旅行用チラシはA4判縦型でレイアウトされている。これは旅行用チラシがラックに配置されるという制約によるものである。多くのチラシが上部3分の1に重要なメッセージを配置されている事などを生徒たちに読み取らせる。
さらに、旅行条件(場所・期間・金額・旅行規約など)各チラシに必ず入っている情報を見つけ、旅行チラシの基本的情報が何かを読みとらせる実習を行った。
またチラシのデザイン上の違いも考えさせた。例えば、「格安旅行」と「豪華な旅行」を較べると、「格安旅行」では、チラシに文字情報を多く表示して「お得感のある旅行」をアピールしている事を理解させた。また「豪華な旅行」では、高級感を出すために写真(イラストなど)を中心として、見出しなどの文字も大きくせず「品」のあるフォントを利用してチラシ全体に高級感を持たせる工夫がある事を理解させた。
【5】ターゲットに合った旅行の設定
想定したペルソナが満足できる旅行をチラシの分析をもとに具体的に設定させる。
ペルソナの
- 経済状態
- 家族との旅行か友人との旅行か
- アウトドア派かインドア派か など
それ以外の条件
- 季節はいつか
- 期間はどれくらいか
- 地域はどこか など
細かく設定させることにより旅行計画自体の具体的なイメージを確定させる。
【6】マインドマップを用いて検討する
ターゲットに合った旅行が設定された後に具体的な旅行案にするために、マインドマップを利用した。
初心者にとって「マインドマップに何を書いてよいかわからない」という壁が出来ることがある。「自由に書きなさい」という指導では、躓いている生徒にとって何の効果もない。
各種の設定を考えさせることにより、様々な情報を手にすることが出来る。その情報をもとにマインドマップを作成することで、スムーズな実習を行うことが可能になる。
【7】実際にチラシを作成する
美術の授業ではないので、出来上がりのクオリティは問わない。ポイントは、検討された項目が具体的な形で入っているかである。
検討して出てきた項目であっても、顧客の目を引くために「キャッチフレーズ」のような形に変更する必要がある。概念としては出来上がっていると思っても、チラシという具体的な形にすることにより、内容を明確にすることでできた。イメージの具体化がポイントとなる。
【8】プレゼンテーションを行う
旅行チラシ作成を目的とした実習であったが、さらに仮想的な顧客(ペルソナ)ではなく現実的な顧客(クラスメート)に対してプレゼンテーションを行った。
プレゼンテーションの練習という面もあるが、ここでのねらいは「評価」と「改善」である。
プレゼンテーションを行うことにより、実際に情報発信を行ったので、それに対する「自己評価」が可能になる。さらに、クラスメートよりの「評価」も可能となる。
今までの実習はPDCAサイクルの企画・実行であり、プレゼンテーションを行うことにより評価・改善を行うことが出来た。
実習全体の流れが完結できたと言えるだろう。
【9】まとめ
今回の実習「旅行計画」自体は情報の授業が始まったころより行われているものである。今回は行わなかったけれども、旅行先の情報を調べて現実的な旅行計画にするという方法で行われることが多かったと思われる。
今回の実習は調べる主体を旅行そのものではなく、旅行者(ペルソナ)や旅行チラシを中心としたことである。
実際の社会においても「個人的な計画」よりも「相手に合った計画」を行うことが求められる機会が多くなる。今回の実習はより実践的なものといえる。
今回の実習はコンピュータを使わずに全て座学で行った。もちろんチラシの作成や資料の収集にコンピュータを使う方法も考えられる。今回はあえて使わないことを選択した。
これによりコンピュータリテラシの差を気にすることなく実習が行えた。さらに、生徒たちが作業だけに目を奪われずに「考える]ことに集中することができた。コンピュータをあえて使わないという実習も今後検討すべきであろう。
※第4回全国高等学校情報教育研究大会大阪大会要項から転載
(2012年4月掲載)