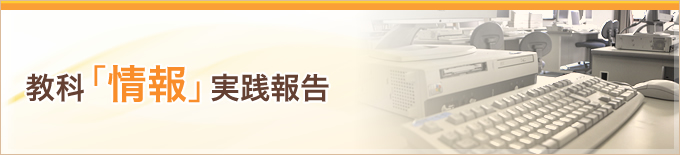- HOME >
- 情報教育 >
- 教科「情報」実践報告 >
- クリティカルシンキングと情報教育
クリティカルシンキングと情報教育
科学的な思考力を育む授業実践
小出 德江(千葉県立成田北高等学校 教諭)

過去も現在もそして日々進歩する情報社会やその未来においても、教育の現場にとって大切なことは、教師ひとり一人が教育の目的を正しく理解し、教科「情報」の目的を見失わないこと。そのためにまず、教師がクリティカルシンキングを身につけ、それを授業へ積極的に導入する具体的な方法を提示し、その実践を通して得られた効果や結果から、これからの情報教育が担う科学的な思考力や表現力の育成方法を提案する。
【1】はじめに
教育の目的とは、人格の完成を目指すものである。よって、各教科の目的は、その授業を通じて、様々な知識、技能、物の考え方や捉え方を身につけ、豊かな心を育むためにある。日々の教育活動を振り返り、授業を行う上でその根本に、「クリティカル・シンキング(Critical Thinking)」という思考法を知らず知らず導入していることに気づいた。これを意識し発展させることにより、より良い授業の構築、教師としての資質向上、生徒の人格形成の一助となることを確信し、これを提案する。
【2】クリティカル・シンキングについて
クリティカル・シンキングの概念の究極のルーツは、ソクラテスの時代にさかのぼる。ソクラテスは、人々が自分自身の非論理的な思考に気づき、自身の理由付けや仮定を吟味し、概念を分析し、関わり合いを説明するための手助けをする質問を投げかけることで人々の論理的な思考を育成するという方法をつくった。この方法は「ソクラテス的発問」として知られ、現在ではクリティカル・シンキングを教える教師がその効果的な教授のために必ずマスターしなければならないテクニックの一つとされている。
クリティカル・シンキングは「批判的思考法」と訳されるが、その概念は、研究者によって様々なものがあり、一致をみていない。それは、クリティカル・シンキングがもつ豊かさやふところの深さを反映していると考えられるが、そのために研究者間でのイメージのずれが生じ、結果クリティカル・シンキングを理解しづらくさせている。
そこで、様々な資料から自分なりのイメージとして、クリティカル・シンキングとは以下の5つの要素も持った科学的・創造的思考であると定義し、教師・生徒ともにクリティカル・シンキングが身につく授業展開を検討し実施した。
- ① 物事の目的を正確に理解する
- ② 偏見や固定概念に囚われることなく、情報や人の意見を鵜呑みにせず自分で考える
- ③ 真実を見極めようと、常に複数の視点から物事を見る
- ④ 自然への畏敬の念を持ち、常に謙虚さや自分が無知であることを忘れない
- ⑤ 常に自分自身を省み、自分の思考が偏っていないか、目的がずれていないかをチェックする(メタ認知)
【3】授業実践「情報A」
3.1 年間授業計画
使用教科書:新・情報A(日本文教出版)
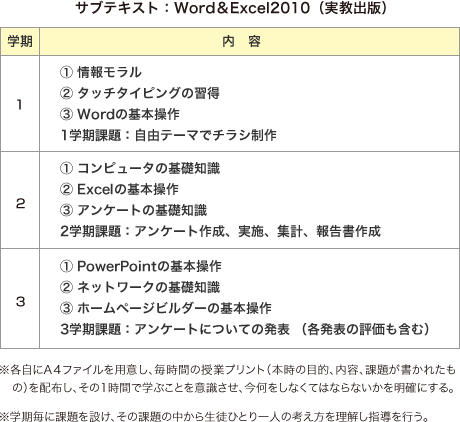
3.2 アンケート作成・発表
教科書の「MISSION5クラスの実態を調査し、分析しよう」を元に、各自のテーマでアンケートを作成し、実施、回収、集計、報告書作成、プレゼン資料の作成、発表、評価を行う。
3.2.1 アンケート作成の流れ(2学期)
- ア 教室で実施
- アンケートについての基礎知識(講義)
- 各自、テーマを決める
- アンケート作成計画書、アンケートの下書き(回答法など)を作成する
- イ CAI室でアンケート作成
- ウ 教室でアンケート実施
原稿を担当者が生徒分印刷し用意する
担当者が配布し、実施、回収し本人へ - エ CAI室でアンケート集計・報告書作成
3.2.2 アンケート発表の流れ(3学期)
- ア PowerPointの基本操作実習
- イ アンケートの発表用プレゼンテーションファイルの作成
- ウ アンケート発表
※各自の発表を評価する - エ アンケートに関する授業で学んだこと
3.2.3 アンケートに関する授業で学んだこと
多くの生徒が、アンケート作成の大変さを実感し、今まで自分が回答してきたアンケートがどのような目的で、どのようにして作られ、集計されてきたか、改めて理解したと感想に書いてくれた。
【4】クリティカル・シンキングの効果
4.1 授業評価
クリティカル・シンキングを導入する以前の授業評価、クリティカル・シンキングを8クラス中1クラスのみ実施した際の授業評価、クリティカル・シンキングを全クラス実施した際の授業評価を比較する。その効果は一目瞭然である。
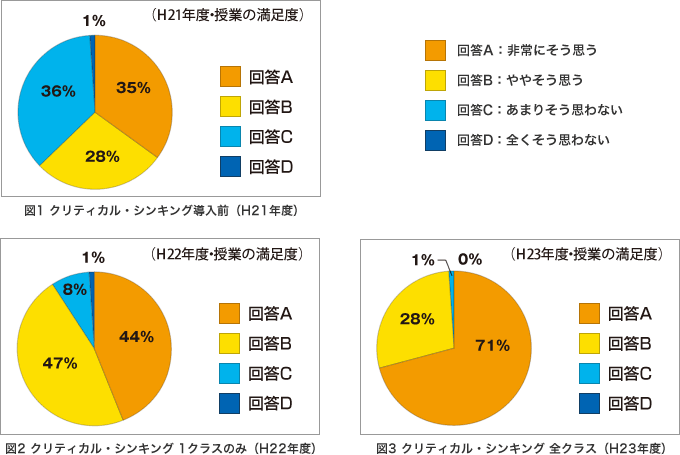
4.2 授業の工夫
クリティカル・シンキングを意識し、次に示す①~③について特に心掛け、授業の工夫を行っている。すると、生徒の様子が変わってくる。授業だけでなく、クラスや学校全体の雰囲気が変化する。
- ① 生徒の氏名を覚え、名前で呼ぶ。
- ② 課題は一人で行う物を用意し、自己対峙の機会であることを意識させる。
- ③ 「頑張れば報われる」システム作りを心掛ける。
【5】本校の概要
多くの先生方が、無意識にクリティカル・シンキングを行い、授業を展開されていると思う。
私自身、年度当初の授業で、ソクラテスの「無知の知」、デカルトの「我思う故に我あり」、ライプニッツの「目的を考えろ」など先人の教えを生徒に伝える。授業を通してクリティカル・シンキングを知らず知らずのうちに身につけさせるよう、学ぶ目的を常に意識させ考えさせる指導を行っている。日々自己を省み、常に進化する姿勢を持ち続けることは、精神的にもかなり辛い。しかし、自分のためと考えず、みんなのためにと考えると心が軽くなる。どんな生徒でも受け入れられる器を作ることが教師にとって一番重要なことであり、「私は何故ここにいるのか」、その存在目的を教師が忘れず、「大人が変われば、子供も変わる」の精神を持ち続け、常に自己の人格の完成を目指し努力を続けることが、教師の仕事であると考える。
参考文献
クリティカル・シンキングと教育(2006)
教育のおけるクリティカル・シンキング(2000)
※第5回全国高等学校情報教育研究会(千葉大会)要項から転載
(2013年2月掲載)