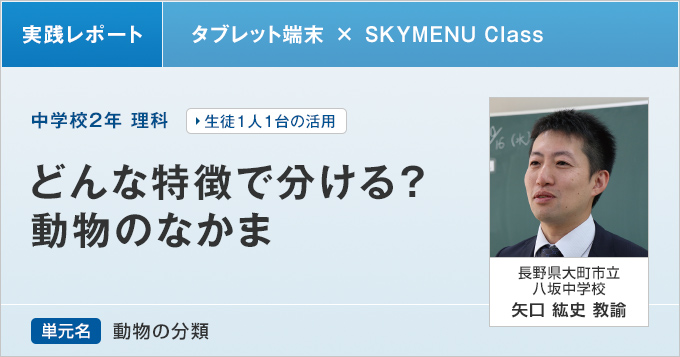![資料集などにあるセキツイ動物の画像を[カメラ]で撮影。分類したいセキツイ動物を[発表ノート]に取り込んだ(写真左)。[画面合体]でお互いの分類や動物の画像を持ち寄り、妥当性を話し合った(写真右)](image/77/img01.jpg)
| 本時のねらい |
生徒自身が選んだセキツイ動物をお互いに持ち寄り、それらの動物がどのような特徴で分類できるか考える場面で、[発表ノート]を用いて、動物の特徴を出し合い、その分類が妥当かどうか話し合うことを通して、分類の観点となる特徴を説明することができる。 |
|---|---|
| 授業の実際 |
はじめに、前時の復習として、前時の分類で使用したセキツイ動物と無セキツイ動物が混ざった画像から、無セキツイ動物を消し、セキツイ動物だけを残した。その[発表ノート]に、さらに自分が思い浮かべたセキツイ動物の画像を資料集などから集め、[カメラ]機能で追加し、それらのセキツイ動物を、見た目、活動場所、子の産み方など、自分なりの観点をもって分類していった。その後、[画面合体]機能で、同じ班の友と画面を共有して、お互いの分類が妥当であるかを話し合いながら、それぞれの端末に動物の画像を飛ばし、班ごと分類を進めた。終末では、[画面合体]を解除して自分の端末に持ちかえった[発表ノート]を、大型テレビに映しながら、班の分類の様子を全体で発表し合い、分類の観点をまとめた。 |
| 単元計画(全7時間) | |||
|---|---|---|---|
| 第1時 |
いろいろな動物をあげ、動物を2つのグループに分類する観点を見つける。 |
||
| 第2時 |
セキツイ動物のなかま分けをしながら、分類の観点となる特徴をグループや全体で話し合う。(本時) |
||
| 第3時 |
セキツイ動物が5つのなかまに分類できることから、それぞれのなかまの特徴をまとめる。 |
||
| 第4時 |
動物のからだのつくりと生活環境について考える。 |
||
| 第5時 |
身近な無セキツイ動物をあげ、無セキツイ動物の分類の観点となる特徴を話し合う。 |
||
| 第6・7時 |
イカやエビなどを観察し、軟体動物と節足動物のからだのつくりや特徴をまとめる。 |
||
| 第8時 |
その他の無セキツイ動物について調べ、その特徴を話し合う。 |
||
| 第9時 |
分類の観点について[マッピング]機能を使ってまとめ、整理する。 |
||
本時の展開
| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |
|---|---|---|
1. 本時の課題をつかむ |
セキツイ動物のからだのつくりについて確認する。 | |
2. 自分なりに考えた観点で分類する |
セキツイ動物だと考えられる動物の画像をタブレット端末に集め、自分なりに観点を考え分類する。 |  [発表ノート]の[カメラ]で動物の画像を撮影し貼り付ける。それを使って分類する。 [発表ノート]の[カメラ]で動物の画像を撮影し貼り付ける。それを使って分類する。 |
3. 動物の特徴を出し合い、その分類が妥当かどうか話し合う |
自分が考えた観点での分類が妥当かを、お互いの分類を見合いながら、グループで話し合い、分類し直す。 |  個人のタブレット端末を持ち寄り、[画面合体]を使って個人で選んだ動物を合わせ、分類し直す。 個人のタブレット端末を持ち寄り、[画面合体]を使って個人で選んだ動物を合わせ、分類し直す。 |
4. グループごとに考えた分類を発表し合う |
グループで話し合った分類を、全体で発表し合い、意見交換する。 |  各グループの画面を大型テレビに投影し、考えを発表し合う。 各グループの画面を大型テレビに投影し、考えを発表し合う。 |
5.分類した観点についてまとめる |
各グループの発表から言えることをまとめ、本時の振り返りを行う。 |
![資料集にある動物の画像を[カメラ]で撮影し取り込む](image/77/img02.jpg)
動物の画像が並んだ[発表ノート]を教員機から一斉に配付した。生徒たちは、自分なりに考えた様々な動物を資料集で探し、その動物の画像を、[カメラ]で撮影して取り込んでいった。取り込んだ画像を[発表ノート]に貼り付けた後、トリミングして追究の基になる動物の種類を増やしていった。「これはセキツイ動物かな」「背骨があるからそうだよ」などと、話し合いながら画像を貼りつけていくことで、セキツイ動物の特徴を確認できた。

グループ追究の場面では、個人の[発表ノート]を[画面合体]して、個人で考えた動物の分類の特徴を話し合いながら、自分で選んだ動物の画像を移動させたり、分担して分類の特徴をまとめたりしながら、分類し直していった。様々なからだの特徴について考えを広げ、分類の特徴によって画像を右や左に動かしたりしながら、グループで考えをまとめていった。また、「こうもり」など、分類に悩む動物については、インターネットで調べて分類するなどの追究する姿が見られた。

本校では、ワイヤレスディスプレイ機能を備えたWi-Fiルータを使用し、無線を介してタブレット端末の画面を大型テレビに投影できるようにしている。
本時は、学習者機画面を一覧表示にして大型テレビに投影した。それぞれのグループがどのような特徴を基にして分類したのかを発表し合うなかで、別のグループの分類の仕方を聞いた生徒は、新たな[発表ノート]のページに、友のデータを貼り付けたり、それを基に分類し直したりすることができた。
自分が見つけたものを教材として考えられるから、
授業がより自分事になった
一人一台タブレット端末を持つことで、自分が見つけてきたもの、自分が気づいたものを教材として取り入れて考えることができ、授業がより自分事になると感じた。また、[画面合体]を使うことで、生徒それぞれの端末が一つのグループ分けの枠になり、分類したことが整理しやすい。さらに、画像を行ったり来たり自由に動かせることから、より活発な対話の場面が生まれたと感じている。
(2020年4月掲載)