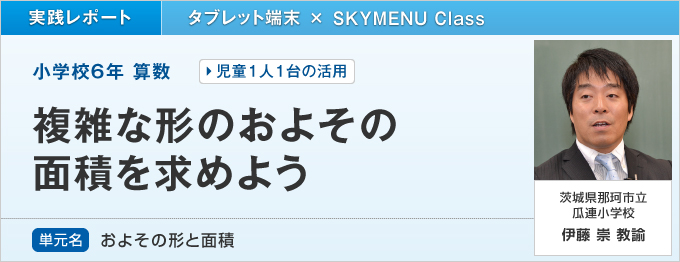![[発表ノート]を使って、児童1人ひとりが琵琶湖のおよその面積の求め方を考えた。児童が考えた求め方は、『SKYMENU Class』を使って素早くグループ、学級全体で共有した](image/52/ttl01.jpg)
| 本時のねらい | 本時は、曲線を含む形のおよその面積の求め方を考える時間である。ここでは、「方眼のます目を数えたり、形を求積可能な図形とみたりして、およその面積を求める方法を理解し、およその面積を求めることができるようにする。」ことを主なねらいとする。 |
|---|---|
| 授業の実際 | 児童に琵琶湖の輪郭のみのイラストを提示し、何の形か想像させることで、本時の課題に対する期待を持たせた。その後、この図形の面積を求めるために必要な情報は何かを考えさせると、5年時の既習である「円の面積」を求める際に活用した「方眼」を活用する考えが出た。そこで、方眼上にある琵琶湖の図を[発表ノート]として配付し、それを活用して求めていくこととした。まずは、自力解決の時間をとり、自身のアイデアで自由に解く時間を設けた。その後、4人1組の学習班になり、タブレット端末の[グループワーク]機能を活用して、班のメンバー全員の[発表ノート]を自身のタブレット端末に集約した。児童らは、このスライドをもとに自分の考えを説明し合う活動を行いアイデアの共有化を図った。最後に、自身が良い考えと思ったスライドを選択し、それらをモニターに投影した。そして、どんなところが良いと思ったかという理由を発表させることで、それぞれの考え方に、場面によって良さや強みがあることに気付くことができた。 |
| 単元計画(全3時間) | |
|---|---|
| 第1時 | 琵琶湖のおよその面積を求める(本時) |
| 第2時 | 曲線を含むいろいろな形のおよその面積を求める |
| 第3時 | 身のまわりのもののおよその面積を求める |
本時の展開
| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |
|---|---|---|
1.本時の学習課題をつかむ |
映像を見て本時の学習課題を確認する。 |  問題場面を示した自作教材をモニターに提示 問題場面を示した自作教材をモニターに提示 |
2.課題を解く |
[発表ノート]に自分の考えをまとめる。 [発表ノート]を使って自分の考えを説明し合う。 |
 デジタルのワークシートを配付 デジタルのワークシートを配付 [グループワーク]機能で班のメンバーの考えを共有 [グループワーク]機能で班のメンバーの考えを共有 |
3.全体で考える |
全体の前で、代表児童が自分の考えを説明する。 | ・複数の考えを画面上に並べ比較 |
4.本時のまとめをする |
児童から導き出された解き方をまとめる。 |
 タブレット端末は、PowerPointで自作した教材を効果的に提示するマシンとして非常に有用であった。本時の場合、琵琶湖の輪郭→航空写真→日本地図へと徐々に提示するスライドを変化させていくことで、求めるべき対象の広さを実感させた。また、児童と対話しながら解決に必要な情報が徐々に表示されていく中で、自力解決への流れがスムーズに行われた。これらのことから、児童の問題場面の理解をサポートするだけでなく、課題に対する児童の興味・関心・集中力を高める効果もあった。
タブレット端末は、PowerPointで自作した教材を効果的に提示するマシンとして非常に有用であった。本時の場合、琵琶湖の輪郭→航空写真→日本地図へと徐々に提示するスライドを変化させていくことで、求めるべき対象の広さを実感させた。また、児童と対話しながら解決に必要な情報が徐々に表示されていく中で、自力解決への流れがスムーズに行われた。これらのことから、児童の問題場面の理解をサポートするだけでなく、課題に対する児童の興味・関心・集中力を高める効果もあった。
![配付された[発表ノート]に考えを書き込む](image/52/img02.jpg) 児童の自力解決の場面では、教師側で予め作成した[発表ノート]の教材を配付し、自身の考えを書き込む活動を行った。普段は、紙に黒、赤、青の鉛筆と定規を使って考えを表現していくが、タブレット端末にはカラフルかつ手軽に描画できるツールが豊富に存在している。児童は、いかに自分の考えをわかりやすく表現するかを考えながら、それらを巧みに活用していた。また、[発表ノート]は児童自らコピーして増やせる。これらの結果、多くの児童から多様な考えが導き出された。
児童の自力解決の場面では、教師側で予め作成した[発表ノート]の教材を配付し、自身の考えを書き込む活動を行った。普段は、紙に黒、赤、青の鉛筆と定規を使って考えを表現していくが、タブレット端末にはカラフルかつ手軽に描画できるツールが豊富に存在している。児童は、いかに自分の考えをわかりやすく表現するかを考えながら、それらを巧みに活用していた。また、[発表ノート]は児童自らコピーして増やせる。これらの結果、多くの児童から多様な考えが導き出された。
![[グループワーク]でスライドを共有して話し合う](image/52/img03.jpg) [グループワーク]機能を活用し、班のメンバーのスライドを自身の端末に集約させる。このスライドをもとに自分の考えを説明し合う活動を行った。全員分の考えを自分の手元にある端末で確認できるので、考えの比較が容易となる。全員がメンバーに説明した後、自身の考えも含め、一番良いと思った方法を選択させ、その理由を考えさせた。この活動を通して、それぞれの考え方には一長一短があり、場面に応じて適切な方法があることに気付くことができた。
[グループワーク]機能を活用し、班のメンバーのスライドを自身の端末に集約させる。このスライドをもとに自分の考えを説明し合う活動を行った。全員分の考えを自分の手元にある端末で確認できるので、考えの比較が容易となる。全員がメンバーに説明した後、自身の考えも含め、一番良いと思った方法を選択させ、その理由を考えさせた。この活動を通して、それぞれの考え方には一長一短があり、場面に応じて適切な方法があることに気付くことができた。
学習者主体の授業へと大きく変換できるツール
タブレット端末は、「イメージしたものを形として表現する」ために、非常に便利なツールであると感じる。教師の「こんな授業を行いたい」や、児童の「こんな考えを伝えたい」といったアイデアを、タブレット端末が持つ様々な機能が、サポートし実現してくれる。特に、児童は教師が思っている以上に使いこなせるようになるので、教師側も積極的に実践を重ね、効果的な活用法を模索していきたい。また、『SKYMENU Class』は、教師主体のタブレット端末の活用に加え、学習者主体の授業へと大きく変換できるツールであると考える。自身の考えを他者のタブレット端末に表示させたり、他者の考えを自身のタブレット端末に表示させたりすることで、各教科の見方、考え方を広げたり、深めたりすることができると考える。
(2018年6月掲載)