
| 本時のねらい | 前時までに、1~9の段の九九の構成をアレイ図等を活用して学習してきた。本時では、何を被乗数・乗数にするかで式が変わる。既習事項を活用し、1つの数の求め方を多様に考え、乗法についての理解を深めさせたい。 |
|---|---|
| 授業の実際 | まず、前時に学習したことを振り返り、今までの学習を想起した。次に本時の学習で活用する図を大型テレビと黒板に提示し、どこに何があるかを確認した。何を「ひとまとまり」に考え、どんな式になるかを個人で考えさせ、ワークシートに記入させた。次に、3~4人の班に分かれ、ワークシートに記入したことを意見交流させた。タブレット端末に配付した[発表ノート]に[マーキング]をさせて交流もさせた。[グループワーク]機能を使えば、他の班の[発表ノート]をお互いに見ることができるので、それをヒントとさせたり、他の式を考えさせたりすることができた。最後に、児童の[発表ノート]を大型テレビに投影し、班で考えた式と理由をその場で説明させた。タブレット端末を活用することで、配付や回収、黒板への移動などの時間を減らすことができるので、その時間を意見交流の時間に充てることができた。 |
| 単元計画(全17時間) | |
|---|---|
| 第1~6時 | 6の段、7の段の九九の構成を理解し、習熟する |
| 第7~12時 | 8の段、9の段の九九の構成を理解し、習熟する |
| 第13時 | 1の段の九九の構成を理解する |
| 第14時 | 倍概念の基礎を理解する |
| 第15時 | 1つの数の求め方を多様に考え、乗法についての理解を深める(本時) |
| 第16時 | 九九を活用して問題を解決し、乗法についての理解を深める |
本時の展開
| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |
|---|---|---|
1. ふりかえる |
・ 前時までの学習をふりかえる。 |
|
2. つかむ |
・ 問題文を提示する。 ・ 気づいたことを発表する。 ・ 課題を提示する。 |
・ 大型テレビに図を投影し、[マーキング]をすることで、どこのことを言っているのかを確認する。 |
3. 解決する |
・ 自分の考えをワークシートに記入する。 ・ 班の中で発表し合う。 |
|
・ 班でわかりやすい求め方をまとめる。 |
・[グループワーク]で、他の班の[発表ノート]をいつでも見られるようにする。 |
|
・ わかりやすい求め方、違う求め方を全体に発表する。 |
|
|
4. まとめる |
・ 黒板にまとめ、データとして残す。 |
![前時の[発表ノート]を投影して、学習を振り返る](image/35/img01.jpg) 導入では、前時で学習した教科書を投影した。大切な言葉などを隠して提示することで、児童がどの程度覚えているかを楽しみながら確認することができる。また、[マーキング]を活用することで、教師が説明している部分を映像でも確認できる。今回は活用しなかったが、前時の学習で使用した[発表ノート]を活用して振り返ることもある。
導入では、前時で学習した教科書を投影した。大切な言葉などを隠して提示することで、児童がどの程度覚えているかを楽しみながら確認することができる。また、[マーキング]を活用することで、教師が説明している部分を映像でも確認できる。今回は活用しなかったが、前時の学習で使用した[発表ノート]を活用して振り返ることもある。
![[グループワーク]で他の班の考えを共有できる](image/35/img02.jpg) [グループワーク]機能により、他の児童や班がまとめた[発表ノート]を見ることができる。班での意見交流が行き詰まったとき、それをヒントとさせたり、他の考えを探すときに活用できる。教師が児童の画面を確認することができるので、紹介したい考え方や記入例を素早く投影できる。学級全体での確認に役立てている。
[グループワーク]機能により、他の児童や班がまとめた[発表ノート]を見ることができる。班での意見交流が行き詰まったとき、それをヒントとさせたり、他の考えを探すときに活用できる。教師が児童の画面を確認することができるので、紹介したい考え方や記入例を素早く投影できる。学級全体での確認に役立てている。
![大型テレビに投影し、自席で[マーキング]しながら発表](image/35/img03.jpg) 意見発表は、移動時間を削減するために児童の座席で行った。[発表ノート]に[マーキング]しながら説明することで、考えがより相手に伝わりやすくなる。また、書き直しを何度しても綺麗にまとめることができる。
意見発表は、移動時間を削減するために児童の座席で行った。[発表ノート]に[マーキング]しながら説明することで、考えがより相手に伝わりやすくなる。また、書き直しを何度しても綺麗にまとめることができる。
最後に[発表ノート]を提出させデータとして残している。[発表ノート]の提出は、プリントの配付・提出より時間を短縮することができ、データを残すことで次時の学習の振り返りに役立つ。
タブレット端末を活用することで
言葉と図が結びつき、子どもの理解度が増す
言葉と画像を合わせることで、説明する側の意図が伝わりやすくなる。低学年なので、タブレット端末やソフトを上手に扱うこと、キーボードやペンで文字を入力することは難しい。しかし、教師がタブレット端末を活用した学習を1年生の時から少しずつ行うことで、班で協力し合い学習に活用することができるようになった。タブレット端末を活用することで言葉と図が結びつき、子どもたちの理解度が増すため、今後もいろいろな場面で活用していきたい。
(2017年5月掲載)

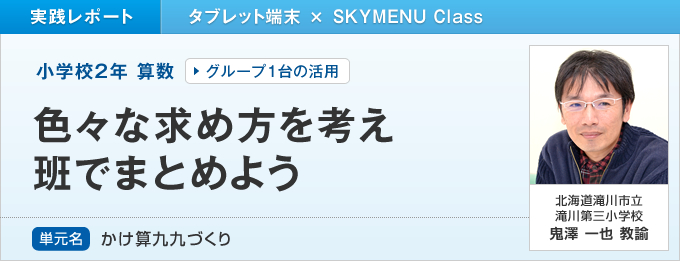
 前時に学習した教科書を大型テレビに投影する。
前時に学習した教科書を大型テレビに投影する。 わかりやすい求め方を[発表ノート]にまとめる。
わかりやすい求め方を[発表ノート]にまとめる。 各班の[発表ノート]をテレビに投影し、その場で図に[マーキング]をさせながら、考えを発表させる。
各班の[発表ノート]をテレビに投影し、その場で図に[マーキング]をさせながら、考えを発表させる。