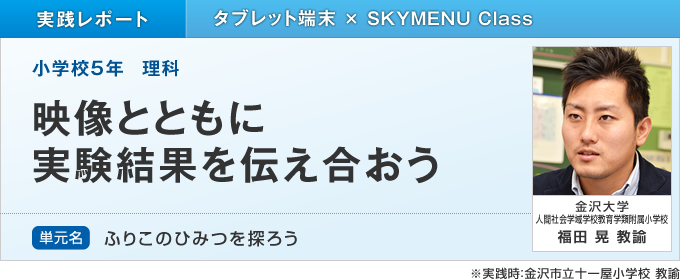| 本時のねらい | 「ふりこが一往復する時間は、何に関係しているか」を予想した後に、実験方法を考えた。前時では、「はなす角度」に関する実験を行った。 |
| 授業の実際 |
ジグソー学習を取り入れ、4人で構成される学習班を「A」と「B」の2つのグループに分け、隣の班の同じアルファベットのグループ同士で新たに4人のグループを作って実験させた(「A」と「B」はそれぞれ異なる条件で実験させた)。 実験後、元の学習班に戻って結果と考察を伝え合うことで、ねらいに迫れるような手立てを取った。 なお、2人に1台のタブレット端末を持たせ、伝え合う際に、活用できるようにした。 児童らは、ふりこが一往復する平均時間と撮影した動画を同時に見せながら説明していた。 平均時間を示すだけではなく、その様子を即座に動画で確認することができていたため、「本当だ。変わっていないね」や「確かに変わっているね。もう一回見せて」といったやりとりが見られた。 |
本時の展開
| 学習の流れ | 主な学習活動 | 指導のポイント (タブレット端末活用場面) |
| 1.課題を確認する | ・まだ調べていない4つの条件が何であったか 確認する |
・ 条件制御について確認する |
| 2.それぞれの条件 の実験をする |
・ 各班を「A」、「B」2つのグループに分け、隣の班の同じグループ同士で集まり実験を行う <調べる条件> A:ふりこを置く高さ/おもりの重さ B:おもりの形/糸の長さ |
ラ]機能で撮影 |
| 3.実験結果を伝え 合う |
・ 所属するグループに戻り、実験結果を伝える | 験結果を示す |
| 4.考察する | ・ 実験結果からどんなことがいえるかを考える | ・結果をもとに考察させる |
| 5.学習をまとめる | ・ 学習課題に立ち返る ふりこの一往復する時間は、糸の長さに関係している |
確認する |
| 単元計画(全8時間) | |
| 第1次 | ふりこにはどんな特徴があるのかな ふりこの一往復する時間には何が関係しているのだろう |
| 第2次 | ふりこの一往復する時間を計る実験方法とは!? おもりをはなす角度は一往復する時間に関係しているのだろうか 残りの条件のうち、どの条件が一往復する時間に関係しているのだろう(本時)実験結果からどんなことがいえるのだろう |
| 第3次 | ふりこのきまりをつかっておもちゃをつくろう |
 調べた条件について発表する時に一往復する平均時間のみを伝えるのではなく、「様子を映像で示すことができると、実験していない人は納得する」ということを事前に伝えておいた。
調べた条件について発表する時に一往復する平均時間のみを伝えるのではなく、「様子を映像で示すことができると、実験していない人は納得する」ということを事前に伝えておいた。
学習班に戻って説明できるように、[カメラ]機能で実験の様子を動画で撮影し、「デジタルワークシート」に保存する様子が見られた。
 学習班に戻り、タブレット端末で撮影した映像と一往復する平均時間を伝え合うことを通して、ふりこが一往復する時間は何に関係しているかをまとめさせた。
まとめは、紙のワークシートに記述させた。
学習班に戻り、タブレット端末で撮影した映像と一往復する平均時間を伝え合うことを通して、ふりこが一往復する時間は何に関係しているかをまとめさせた。
まとめは、紙のワークシートに記述させた。
平均時間の計測結果を見るだけではなく、「デジタルワークシート」に保存されている映像で示して説明することで具体的な共有化が行われていた。
 どの班でも、「ふりこが一往復する時間は、糸の長さに関係している」という結論を出していた。全体で確認した後、ふりこの長さと時間についての関係を問うたところ、「糸の長さが長くなると一往復する時間は長くなる」という反応が返ってきた。そのことを全体で確認するため、予め教師が撮影しておいた「糸の長さを変えた実験の動画」を大型ディスプレイに提示した。同じ動画を即座に何度も繰り返し視聴できたため、共通理解が促進された。
どの班でも、「ふりこが一往復する時間は、糸の長さに関係している」という結論を出していた。全体で確認した後、ふりこの長さと時間についての関係を問うたところ、「糸の長さが長くなると一往復する時間は長くなる」という反応が返ってきた。そのことを全体で確認するため、予め教師が撮影しておいた「糸の長さを変えた実験の動画」を大型ディスプレイに提示した。同じ動画を即座に何度も繰り返し視聴できたため、共通理解が促進された。
タブレット端末で、実験の様子を撮影し、映像とともに結果を示すことによって、具体的な共通理解が行われることとなった。また、各班でまとめる際に、必要に応じて映像を再視聴している姿も見られた。同じ映像を必要な時に何度でも繰り返し視聴できることが非常に有効であったといえる。一方で、タブレット端末の操作に固執してしまい、実験の事象に注目できない児童がいたのも事実である。タブレット端末の操作に慣れさせていくということも必要だと考えた。
(2014年5月掲載)